2018.10.29
【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「色と形」(第3回)の授業を紹介します。
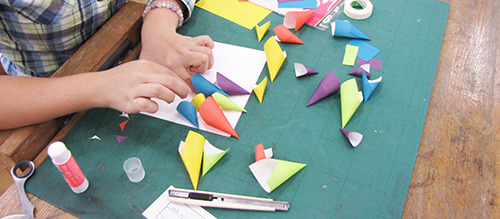
授業科目「鑑賞のための造形演習」
「色と形」(第3回)
平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションの学生は必修)の「色と形」(第3回)の授業を紹介します。
「鑑賞のための造形演習」は、全員が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。作品を掲示し、心動かされたもの、共感できるもの、直感的に選んだもの、なんとなく良いと思うものに、白テープを貼って投票します。投票することによって、自分自身の価値観や見方を認識し、さらにそれ以降の鑑賞眼が高まっていきます。
<第3回授業>の制作課題
「色紙:課題6」
今日の自分を表現する色紙作品を制作しなさい。制作時間は50分。鑑賞して良いと思う作品にテープを貼って投票する。
以下は 課題6(今日の自分を表現する)の制作風景
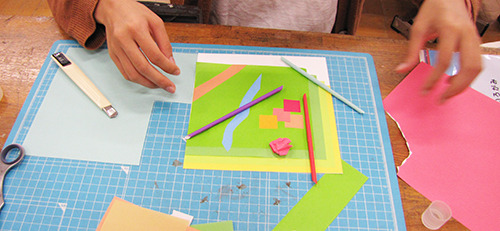




以下は課題6の学生作品






以下に、第3回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします)
「色紙:課題6」(今日の自分を表現する)
<課題6の全作品を鑑賞した感想は>
「“自分を表す”という言葉に救われた。他人に見られる意識を捨てて制作できた」、「そんなに凝っているわけではないが心情を表しているのをみると良いねってなる」、「個性が出ていた。情熱的なもの、静かなものなど自由な表現がされていた」、「色紙の課題6までで、今回の課題が自分の中で一番納得のいく作品ができた」、「似た作品が1つも無くて驚いた」、「今日の課題6が一番カオスな印象を受けた」、「混色が増えた。感情に結びつける作品が多くみられた」、「この課題で初めて自分のやりたいように制作することができた」、「それぞれの人の今の気持ちが可視化されると全員が全く違うんだと思った」、「自分を表現する課題は非常に作りやすかった」、「強く自分を表現していることが伝わってくる作品ばかりで、共感できるものもあれば、できないものもあった」、「自分と向き合っても表現したいことが無いと気づいた」、「今回は心情に響く作品が多かった。内情を表現したと思うと深く考察したくなる」、「やりたいことをやった作品が多く、これ以前のミッションや評価から解放されたからだろう」、「共感できるという基準から投票にばらつきがあり、切り方に技術を必要とするものばかりではなくなった」、「課題6は見ごたえがあり、色紙だけでここまで表現きるのに驚いた」、「評価を気にしないということだったの心穏やかに取り組めた」、「心の苦悩を感じる作品に目が行った。若者の心の表現が様々で必ずしもダイレクトではなかった」、「濁っていない色のキレイな作品が減った。他人に良くみられたいという意識が除かれたからかもしれない」
<「革新的」・「自己表現」・「芸術」の3語を用いて自由に論述しなさい>
「美術は楽しいから続けられる。楽しさをなくして他人の評価ばかりを気にするのは違う」、「芸術は自由だというけれど、革新的な表現をしても社会に受け入れられるようなものではないと評価されない」、「自分らしくないものを作ることが逆に私の革新的な部分につながると思って制作した」、「私はある人に注目して見てきた。課題3までは目立たず票が入る作品ではなかった。課題4から作品が立体的に変化したことに気づいた。課題6で紙をくしゃくしゃにした表現に発展し、革新的な作品だと感じた」、「結局は自分の納得する形で出したものを認めてほしいのだと思う。他者を意識しながら自分本位なものづくりは良くないと思うが、欲望であるならそうであってほしい」、「デザイナーを目指していると現実的なデザイン思考に固まりがちだ。芸術性のようなものを忘れてしまいがちだが、自分のフラストレーションを爆発させる作品を共有することで革新的なアイデアを生み出せる」、「革新的とは何なのか。私の作品は人の踏襲にすぎず、真似っこで、新しさなどどこにもないのではないかと自己嫌悪に陥った」、「自分を表現したい作品と、自分を理解してほしい作品にわかれ、後者は解釈に余白を設けて鑑賞を飽きさせない」、「鑑賞する方も、私はこう感じたという自己表現ができるのがおもしろい」、「自己表現の自我は鑑賞者がいると相対的なものになる。相対的な自我は自分ではないと断言できないが、自我の本質や自我の核が表現されているとも思えない」、「コンピュータやインターネットでの自己表現は今日的な自己表現手段だ。表現手段を増やしてきたのは人々が革新を求めた結果だといえる」、「芸術はただの自己表現ではないと感じた。他人の評価より自分の表現を優先できるようになりたい」、「芸術は己と作品に向き合い自己表現を高めていくものだ。評価を意識すると打算と下心が生まれる。それが全てではないとわかっていながら他人を意識せざるを得ない」、「この授業は芸術文化学部の学生であることを強く意識させてくれる。デザインの授業ではクライアントやターゲットありきで進めていくため、この授業の自己表現は新鮮だ。芸術とデザインの共通を考えると革新的アイデァだと考える」、「課題6で自己を表すのに、課題5までの技法を捨て去った作品が多い。自己表現は自己満足の域であり、そこに他者の目は介在しない」、「体で表現する、言葉で表現する、モノで表現するなど性格の異なる方法はそれぞれアイデンティティーを持ち、その表現でしかできないものもある。いろいろ試してみると自分を理解することにつながる」、「人は芸術作品に何を見いだしているのか。これまで分からなかったことがますます分からなくなった。革新的に制作したつもりが、他人の作品と並べるとそう見えなくなる。作品は作者の意思、鑑賞者の意思によっても違う顔を見せる」、「芸術に確かなものは何もなくて不安定だなと体験から理解するに至った」、「日常的に行動などで自己表現しているのに、この場(今回の授業)では妙に心を暗くする。それは自分の力をそそぎこんだと思っているからだろうか」、「革新的な課題の時は他の制作者や鑑賞者を意識し、票を入れる時も他の人が見ても新しいものかを基準にしていたが、今回の自己表現の課題では他人への意識は無く、自分がどう表現するか、何に共感するか、ばかりを考えていた」、「現代の作品のほうが過去の宗教画、風景画と比べ作者の心理を表現できている」、「革新的作品は必ずしも評価されるものではなく受け入れられないものもある。他人の評価を気にしてばかりでは自分の表現を深められない」、「芸術となりうるものは、見られることもわかったうえで、それでも自分の中のものを表現した作品だ」、「大賞狙いの作品で、複雑な表現が多くの票を得たことから評価者は技術も評価の内と意識している」、「課題3と4に一票も入らなかったが、これらは票を入れてほしいと思って制作したものだった」、「自己表現の課題で心情をありのまま表現するうちに新しい表現が浮かんだ。他人には革新にみえないかもしれないが自分には革新だった」、「革新は次元の限られた、意識の方向の限られたものではなく、多次元的な方向や様々な見方、異世界的な方向へ向かう考えであるため、自らが生きている間に革新を意味づけることは困難」、「革新と自己表現から、芸術のテーマが自分の外にあるときと内にあるときで作風は大きく異なる」、「課題6の作品で良いと思う作品ばかりで、ダメだと思うものは1つもなかった。このことによって自己表現する制作へのハードルが下がったように感じた」、「芸術は新しいものを作り続け、社会全体が抱いていたイメージを破壊し続けるものだと考えていた。意識するほどに新しい表現を生み出すことは難しく、他人からの影響を受けないで自己表現することも難しいと感じた」
<「近未来」・「制作」・「鑑賞」の3語を用いて自由に論述しなさい>
「制作者と鑑賞者を行き来することで、どちらの視点も大切だと気づいた。誰からも投票されなくても教室にいる人の評価であり、鑑賞する人が違えば評価も変わることがわかった」、「鑑賞してその人の芸術を学び自分に生かす、つまり自分の鑑賞が近未来の自分を成長させるような気がして学びが多い時間だった」、「これまでの授業は、制作と鑑賞のどちらかに偏っていたが、この授業で2つを行き来するのは新鮮で、この機会に多くの発見をしたい」、「制作と鑑賞は時間を越えた行為だと気づいた。過去に制作されたものがあって鑑賞することができる」、「制作するとき、我々は常に何かの固定観念にとらわれながらつくっているのだ」、「子どもの美術の授業に評価は無く、ありのままの表現をして欲しい。美術をとおして心を養うものとして残って欲しい」、「SNSやコンピュータの発達により他人からの評価を受け取りやすい。今よりももっと革新的な作品に出会えるかも知れない期待がある」、「これからの制作者はさらに革新的作品を目指すだろうが、多くの人が楽しめる芸術は残っていくだろう」、「鑑賞は、制作したことへの労いや肯定する意味として大切。小学校や中学校の図工や美術の時間でできるだけ早く今回のような授業が盛んにおこなわれて欲しいと思った」、「教員に評されない鑑賞は初めてだった。教員一人だと教員の好みに偏った講評になる。多数の学生の好みが分かれるのがおもしろかった」
[受講生]
2〜4年生対象
*平成29年度以前入学生対象
[必修科目となるコース]
芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース)
*他のコースは選択科目
[担当]
三船 温尚(芸術文化学部 教授)