2018.01.23
【学生の日々】GEIBUN9卒業制作紹介!文化マネジメントコース 奥垣内 美来

「文化財建造物修復における、塗装修復は本当に修復といえるのだろうか 〜厳島神社を例として〜 」
今回紹介するのは文化マネジメントコース 奥垣内 美来 さん。
テーマは「文化財建造物修復における、塗装修復は本当に修復といえるのだろうか〜厳島神社を例として〜 」です。
(「文化マネジメントコース」は平成27年度より「芸術文化キュレーションコース」へコース名が変更になりました。)
Q.研究の内容を教えてください。
A.文化財建造物での外観の塗装修復が、復原修復という修復方法の考え方に本当に沿っているものなのかを明らかにします。そもそも復原修復というものの定義は何なのかを明確にすることが目的です。
Q.興味を持ったきっかけは何ですか?
A.元々、伝統技術が好きで2、3年生の時には漆の授業もとっていたんです。卒業論文を書くなら、自分が4年間でやってきたことをテーマにしたいと思うようになり、漆をしたいと考えました。それで、自分の原点は何かを考えてみると、元は建築や神社仏閣が好きで、構造や天井も好きで、好きなことを調べるなら漆と建築だと思いました。さらに4年間で旅行も好きになったし、その中で世界遺産も好きになったので世界遺産、神社仏閣、漆に関わることをしたいと思いました。そこで、世界遺産の神社仏閣で漆が使われているものを探して、好きなものを盛り込んだ結果が今のテーマです。題材の厳島神社も地元である広島にあり、代表的な観光地です。自分の原点回帰に時間がかかり何をテーマに研究するかはギリギリまで悩みました。
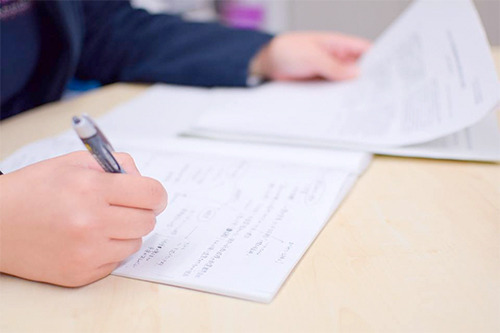
Q.テーマの「修復といえるのだろうか」というのは、例えば『厳島神社の剥げてきたところを赤く塗装して綺麗に直すことは正しいのか?』ということでしょうか。
A.そうですね、具体的にいうと塗装修復は一度剥いでから、塗り直すことが基本で、色を作り直して塗り替えています。漆とかは気温・湿度によって、同じ材料・分量でも色が変わってくるので職人さんでも同じ色はほぼ不可能に近いそうです。色を合わせる時に、材料に何を使っていたかは、最新の技術で明らかにすることができますが、実際に色を作り出すっていうことには、どうしても明確なものがなくて、写真もなく、今見ている色が本当に当初の色なのか分からない場合もあります。難しいところだと思いました。
塗装修復は全く同じ色がでない状態で塗り替えの修復を行うと外観のイメージに差異が出るのではないか。復原修復は元の材料を使って昔あった状態に戻すという作業だから、昔と同じ色でないとダメなんじゃないか。そう思い、研究してみることにしました。
Q.修復した箇所がわかるように塗り直すものなのですか?
A.試し塗りはありますが、修復した部分を修復したか分からないようにする、周りと同じような色になるというのはおかしくて、ちゃんと修復したことが分かるようになるはずなんです。当初から、塗って何年も経って色褪せた今の状態に合わせることはおかしいし、修復した事実が分からないというのも良くないのではないかという複雑な感じです。
調べた中では、修復した部分が分かるようにした方が良いという資料もありました。実際に厳島神社は塗り直したかどうかを分かりやすくしてあるようにしてあると思います。でも、さっきも言ったように、修復前の状態は以前塗り直されてから何年か経った状態の物です。なので、分かりやすく直すというよりは、当初の景観を再現すると必然的に鮮やかな色になってしまうということだと思います。景観の印象がだいぶ変わってしまうのですが、海外の教会の壁画や日光東照宮でも同じようなことが言えると思いました。

Q.特にこだわっている部分を教えてください。
A.「文化財建造物の修復」ということで、建築的な目線で構造の話や木の台風の損壊などの復原について言われることが多いです。しかし、建築的考えだけではなく、芸術的な面からもピックアップしてやっていきたいと思っていて、外観の修復に絞って調べています。深く難しく考えずに建築に興味がない人にも見て欲しいです。
Q.研究している上での気付きはありますか?
A.最近、文化庁から文化財修復に関する新たな方針が出ていて、数年後に「文化財建造物の修復に使う漆は国産100パーセントにしよう」という試みが提示されていることを知りました。今は生産量が少ないから、最後の仕上げだけにしか使っていないけど、平成30年からは工程で使用する漆は全て日本のものにするという方針が出ていました。会見映像がYoutubeで公表されていて、こうやって調べないと公式に発表されていても知らないことがあるということに驚きました。
今は国産3割、中国産7割ほどで修復していて、保存という定義からみると昔使っていたものを使わないといけない訳だから、国産にしないといけないのではないかというのは感じます。
漆の英訳は”japan”っていうほどの伝統的な材料なのに、国産漆の生産量は年々減少しています。中国産の漆は日本産より安いので、需要の減少が原因かなと思います。この政策が成功することで、国からの需要が高まり、その現場を改善することもできると考えました。
Q.今後の意気込みをお願いします。
A.展示の方法としては、写真を展示することで内容を分かりやすくして、みんなに気軽に手に取ってもらえるものにしたいです。よくA4用紙1枚にまとめた説明だけを取っていく方はいますが、そうではなく、論文も手にとって本文に目を通してもらえるようにしたいです。
ありがとうございました。
[取材・写真・文・編集]
卒展キュレーター委員会 (2017年11月8日)